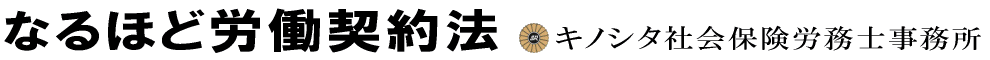片山組事件
片山組事件 事件の経緯
入社して21年以上、建築工事現場で現場監督業務に従事していた従業員が、バセドウ病に罹患しました。
会社から現場監督業務に従事するよう業務命令を受けましたが、従業員は病気のため、現場作業に従事できないことを申し出ました。
会社から診断書を提出するよう求められたため、従業員は「現在、内服薬にて治療中であり、今後厳重な経過観察を要する。」と記載された診断書を提出しました。
会社は、健康面や安全面で問題が生じる恐れがあることから、現場監督業務に従事することは不可能と判断して、従業員に当分の間は自宅で治療するよう命じました。
これを受けて従業員は再度、「現在経口剤にて治療中であり、甲状腺機能はほぼ正常に保たれている。中から重労働は控え、デスクワーク程度の労働が適切と考えられる。」と記載された診断書を提出して、事務作業を行いたいと会社に申し出ました。なお、従業員は、臨時的一時的に、図面を作成するなど事務作業に従事したことがありました。
しかし、会社は、現場監督業務に従事できないことを理由に、自宅治療の命令を継続しました。
その後、病状が回復して、従業員は現場監督業務に復帰しました。会社は、従業員が復帰するまでの約4ヶ月間は欠勤扱いとして、その期間の賃金を支給しませんでした。また、賞与も減額して支給しました。
これに対して従業員が、自宅治療の命令は無効であると主張して、欠勤扱いとされた期間の賃金と減額分の賞与の支払いを求めて、会社を提訴しました。
片山組事件 判決の概要
従業員が職種や業務内容を特定しないで労働契約を締結した場合は、現に就業を命じられた特定の業務を完全には遂行できないとしても、その従業員の能力、経験、地位、会社の規模、業種、配置・異動の実情や難易等に照らして、その者が配置される可能性がある他の業務を遂行できて、かつ、本人もそれを申し出ているのであれば、労務を提供していたとみなされる。
そのように考えないと、同じ会社で同様の労働契約を締結した従業員が、身体的な原因で提供できる業務に制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等に関係なく、現に就業を命じられている業務によって、賃金の請求権の有無が左右されることになり、不合理である。
従業員は、会社に雇用されて21年以上にわたって建築工事現場で現場監督業務に従事してきたが、労働契約上、職種や業務内容は現場監督業務に限定されていない。また、従業員が自宅治療の命令を受けた当時、事務作業に従事することが可能で、かつ、本人もそれを申し出ていた。
そうすると、直ちに欠勤扱いとすることはできず、従業員の能力、経験、地位、会社の規模、業種、配置・異動の実情や難易等に照らして、従業員が配置される可能性のある業務が他にあったかどうかを検討するべきである。
また、従業員は、「現場監督業務に従事していた者が、病気やケガ等によって業務に従事できなくなったときに、他の部署に配置転換された例がある」と主張しているが、その点について、認定や判断が行われていない。
片山組事件 解説
病気のため、現在の配属先の業務(現場作業)はできないけれども、別の部署で事務作業は行える状態になりました。会社は自宅治療を命じて、欠勤扱いにして約4ヶ月賃金を支払いませんでした。それで、従業員が賃金の支払いを求めて裁判になったケースです。
裁判所は、職種や業務内容を特定しないで労働契約を締結した場合は、現在の配属先で完全には業務を遂行できないとしても、従業員の能力、経験、地位、会社の規模、業種、配置・異動の実情や難易等に照らして、その者が配置される可能性がある別の部署で業務を遂行できて、かつ、本人もそれを申し出ているのであれば、労務を提供していたとみなされると判断しました。
つまり、欠勤扱いとすることは不可能で、会社は賃金を支払う義務があるということです。
会社の裁量で配置転換を行えるのであれば、配置転換を検討する必要があります。会社が配属先を決定して、たまたま体力的に厳しい部署に配属されて、病気になって勤務できない状態になったとすると、軽易な部署に配属された従業員とは不公平になってしまいます。
会社は自由に配置転換を命令できる権限がある反面、このような場面においては責任が生じます。一方、職種や業務内容を限定して雇用契約を締結していた場合は、配置転換を検討する必要はありません。
従業員が配置転換を申し出ていることもポイントです。配置転換を行える余地があったとしても、本人が申し出ていなければ、会社は配置転換を検討する必要はありません。もちろん、賃金を支払う義務もありません。
この裁判(最高裁判所)では、配置転換を行える余地があったかどうかを検討していないとして、高等裁判所に差し戻しました。その差戻し審では結果的に、事務作業に従事させることは可能であったと判断して、従業員の請求を認めました。
ところで、裁判では、「債務の本旨に従った労務の提供」という難しい言い方をしていて、これがあったかどうかがポイントになっています。
会社と従業員は労働契約の関係にあります。労働契約とは、従業員が労務を提供して、会社が賃金を支給するという契約で、「労務の提供」と「賃金の支給」はそれぞれの義務(債務)です。
そして、民法の第536条第1項で「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。」と規定されています。要するに、従業員の都合で欠勤をした場合は、会社は賃金を支払う義務がありません。
また、民法の第536条第2項で「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」と規定されています。
これを労働契約に当てはめると、会社の都合で従業員が労務を提供できなかった場合は、会社は賃金の支給を拒否できないということになります。
正当な理由がないにもかかわらず、会社が従業員の出勤を拒否した場合は、出勤したものとみなして、会社は賃金を支払わないといけません。従業員に落ち度はなく、会社のミスですので、会社に責任が生じます。
実際には出勤していないとしても、「債務の本旨に従った労務の提供」はあったとみなされます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。