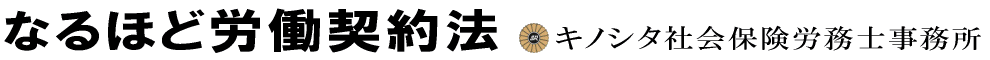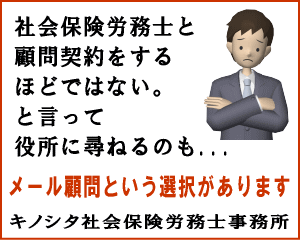三菱樹脂事件(試用期間)
三菱樹脂事件 事件の経緯
大学を卒業して、3ヶ月の試用期間を設けて会社に採用されました。
その後、その従業員が大学在学中に、学生運動に参加していたことが明らかになりました。これにより、会社が採用試験の際に提出を求めた身上書に、従業員が虚偽の記載をしていたこと、記載すべき事項を秘匿していたこと、また、採用面接でも虚偽の回答をしていたことが発覚しました。
従業員のこのような言動は、民法(第96条)にいう詐欺に該当するもので、管理職要員として不適格であると会社が判断し、試用期間の満了と共に従業員の本採用を拒否しました。
これに対して従業員が、本採用の拒否(解雇)の無効を主張して、会社を提訴しました。
三菱樹脂事件 判決の概要
思想・信条の自由を保障する憲法第19条、法の下の平等を保障する憲法第14条は、国と個人の関係を規律するもので、会社と個人の関係を規律するものではない。また、同時に憲法では、第22条で営業の自由、第29条で財産権の行使を保障している。
したがって、会社が自己の営業のために従業員を雇用する際は、法律による制限がない限り、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇い入れるかは、会社が自由に決定できる。会社が特定の思想・信条を有する者の雇入れを拒んでも、違法にはならない。
また、労働基準法第3条は、従業員の信条を理由として、賃金その他の労働条件について差別することを禁止しているが、これは雇い入れた後の労働条件であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。
このように、会社には雇用の自由があり、思想・信条を理由として雇入れを拒んでも違法にはならないから、会社が従業員の採否を決定する際に、従業員の思想・信条を調査し、これに関連する事項の申告を求めても違法にはならない。
そのうえ、本件は、会社が従業員の思想・信条そのものを調査したものではなく、従業員の過去の行動を調査したもので、なおさら違法ということはできない。
しかし、会社が行った本採用の拒否は雇い入れた後の解雇であって、これを雇入れの拒否と同視することはできない。会社は、従業員の雇入れは自由に行えるけれども、一旦従業員を雇い入れた後は自由に解雇することができない。
また、労働基準法第3条は、信条による労働条件の差別的な取扱いを禁止しているが、特定の信条を有することを理由として解雇することは、差別的な取扱いとして、この規定に違反する。
ところで、本件雇用契約は、試用期間中に従業員が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の解約権が留保されていた。
このような解約権の留保は、大学卒業者の新規採用に当たって、採否決定の当初は、会社の管理職要員としての適格性の有無に関連する事項について必要な調査を行い、適切な資料を十分に集められないため、後日の調査や観察に基づいて最終的な決定を留保する趣旨で設けられる。
そのため、留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇とは異なり、前者の場合は後者の場合より広い範囲で解雇の自由が認められる。しかし、留保解約権の行使は、その趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当であると認められる場合にのみ許される。
つまり、会社が、採否決定の当初は知ることができず、又は、知ることが期待できないような事実を、採用決定後の調査や観察によって知ることとなり、その者を引き続き雇用することが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に相当であると認められる場合に限って、留保解約権を行使できる。
したがって、会社が解雇理由として挙げている学生運動への参加の事実の秘匿等について、それが客観的に合理的な理由となるかどうかを判断するためには、従業員に秘匿等の事実があったかどうか、学生運動に参加した内容・態様・程度、特に違法行為があったかどうか、秘匿等の動機や理由等に関する事実関係を明らかにする必要がある。
そして、従業員の入社後の行動や態度、人物評価等に及ぼす影響を検討し、これらを総合して合理的な理由の有無を判断しなければならない。
三菱樹脂事件 解説
試用期間中は労働契約の解約権が留保された状態と考えられていて、通常の(本採用後の)解雇より広い範囲で解雇の自由が認められます。
ただし、試用期間中の解雇であっても(留保解約権を行使する場合であっても)、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合でなければ、有効と判断されません。
つまり、採否を決定した当初は知ることができず、又は、知ることを期待できないような事実が、試用期間中に発覚し、そのような事実を知っていたら採用しなかったという程度の理由が不可欠で、また、その事実関係も明らかにする必要があります。
試用期間の適用を受けるか受けないかによって、解雇の有効・無効の判断が分かれるケースも十分あります。
労働契約法を制定する際の研究会では、従業員に試用期間を適用する場合は、そのことを書面で明示することが検討されていました。
最終的には労働契約法には取り入れられませんでしたが、取り入れられなくても、実際に、試用期間であることを従業員に明示していなければ、通常の解雇と同一視され、広い範囲で解雇の自由が認められない可能性が高いです。
ところで、この裁判は高等裁判所に差し戻されて、その後、会社が解雇を撤回して、従業員が職場に復帰する方向で和解が成立しました。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。