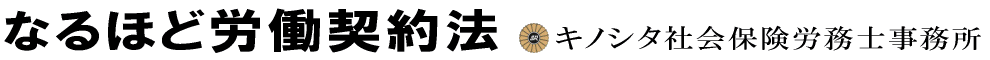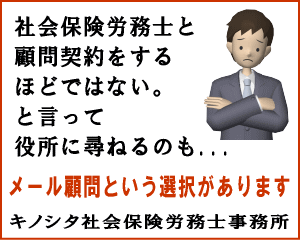日立メディコ事件(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
日立メディコ事件 事件の経緯
臨時従業員として、最初は20日間の期間を定めて会社に雇用された後、2ヶ月間の期間を定めた労働契約に切り替えて、5回更新されました。
その後、人員を削減せざるを得ない状況になったため、会社は臨時従業員の労働契約の更新を拒否して、雇止めをしました。
これに対して臨時従業員が、期間を定めた労働契約が繰り返し更新されたので、期間の定めのない労働契約に切り替わったものと同視できる。
そして、解雇に関する法理を適用するべきであるけれども、希望退職者を募集しないで行った解雇は無効であると主張して、労働契約が存在することの確認等を求めて、会社を提訴しました。
日立メディコ事件 判決の概要
臨時従業員の制度は、景気の変動に伴う受注の変動に応じて、雇用量を調整する目的で設けられたものである。
臨時従業員を採用する際は、面接で健康状態、経歴、趣味、家族構成などを尋ねるだけで、学科試験や技能試験は行わず、簡易な方法で採用を決定することになっていた。
また、臨時従業員は比較的簡易な作業を行い、季節的業務や特定物の製作のように臨時的な作業のために雇用されるのではなく、ある程度は継続して雇用することになっていた。
会社が臨時従業員の労働契約を更新する際は、契約期間が満了する1週間前に、本人に意思確認をして、労働契約書の「雇用期間」の欄に雇用期間を記入して、臨時従業員が押捺していた。
ただし、臨時従業員が所属していた工場では、本人に意思確認をした上で、給料の受領のために預かっているハンコを庶務係が本人に代わって押捺していた。
このように労働契約は、契約期間が満了する都度、臨時従業員と会社が合意して、5回にわたって更新されてきた。
このような者を契約期間の満了によって雇止めをする場合は、解雇に関する法理が類推適用される。そして、解雇権を濫用するなど解雇が無効と判断される場合は、その直前の労働契約が同じ内容で更新されたと考えられる。
5回にわたって有期労働契約を更新したとしても、期間の定めのない労働契約に転換したり、期間の定めのない労働契約が成立したりすることはない。
ところで、臨時従業員の採用手続は簡易で、期間を定めた労働契約を前提とするのであるから、雇止め(解雇)の効力を判断する基準については、いわゆる正社員を解雇する場合の基準とは差異があって当然である。
したがって、事業上やむを得ない理由により、人員を削減する必要があり、その余剰人員を他の部門に配置転換する余地がなく、臨時従業員全員の雇止めが必要な場合は、これに先立って、正社員に対して希望退職者を募集していなかったとしても、それをもって不当、不合理ということはできない。
会社が臨時従業員全員の雇止めを事業上やむを得ないと判断したことについて、合理性に欠ける点は見当たらない。希望退職者の募集に先立って、臨時従業員の雇止めが行われたとしてもやむを得ない。
臨時従業員に対して行った雇止めについては、権利の濫用、信義則の違反があったとは言えないし、当時の状況は就業規則の解雇事由に記載されている「業務上の都合がある場合」に該当する。
日立メディコ事件 解説
有期労働契約の更新を繰り返していた場合に雇い止めをすると、解雇に関する法理が類推適用されて、解雇(雇い止め)は無効と判断されるケースが多いです。
しかし、この裁判例では、正当な解雇事由があったとして、解雇(雇い止め)は有効と認められました。
業務上の都合により、人員を削減する必要がある場合に、正社員と臨時従業員では会社との結び付きの度合いが異なるため、正社員に向けて希望退職者を募集する前に、臨時従業員の雇い止めをしても合理性があると判断しています。
一般的には、解雇をする前に、希望退職者の募集や配置転換などを検討して、最終手段である解雇を回避するための努力をしなければならないと考えられています。
このケースでは、臨時従業員全員の雇い止めを行うことが前提でしたので、解雇は有効と判断されましたが、希望退職者を募集すれば解雇を回避できたかもしれないという状況では、解雇は無効と判断される可能性が高いです。
会社が解雇を回避するために何をするべきか、はそれぞれの状況に応じて異なります。
また、この裁判では、期間を定めた労働契約の更新を繰り返しても、期間の定めのない労働契約に転換することはない、期間を定めた労働契約が同じ内容で更新されると判断しています。
期間の定めのない労働契約に転換する場合は、当事者双方の合意が必要ということですが、労働契約法では会社の意思にかかわらず、期間の定めのない労働契約に転換されることが規定されました。
判例法理は当時の法律の下で、あくまでも考え方を示すものですので、強制力はありません。判例法理の考え方と法律の内容が異なる場合は、当然、法律(労働契約法)の方が優先されます。
【関連する裁判例】

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。