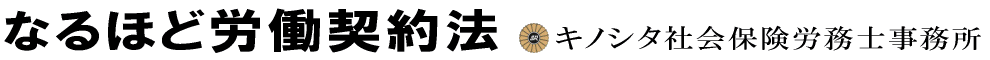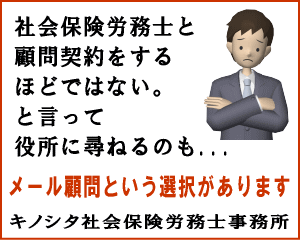朝日建物管理事件
朝日建物管理事件 事件の経緯
会社と従業員は、契約期間を平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする有期労働契約を締結しました。その後、同様の内容で4回更新して、最後に締結した有期労働契約は平成26年4月1日から平成27年3月31日までを契約期間としていました。
なお、労働契約書には、契約期間満了時の業務量、従事している業務の進捗状況、従業員の能力、業務成績及び勤務態度並びに会社の経営状況により判断して、契約を更新する場合があると記載されていました。
会社は配置転換の命令に従わなかったことを理由として、従業員を平成26年6月9日付で解雇しました。
これに対して従業員が、解雇の無効を主張して、労働契約上の地位の確認と解雇日から判決確定日までの賃金の支払いを求めて、平成26年10月25日に会社を提訴しました。
第1審は、有期労働契約の契約期間中の解雇について規定している労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」には該当しないと判断して、平成29年4月27日に、従業員の請求を認容する判決を言い渡しました。
会社は、最後の契約期間の満了日の平成27年3月31日に労働契約が終了したと主張して、控訴しました。
第2審は、会社の主張は時機に後れたものとして、契約期間の満了による雇止めが有効かどうかを判断することなく、第1審と同様に従業員の請求を認容して、平成29年9月14日に終結しました。
朝日建物管理事件 判決の概要
契約期間の満了によって労働契約が終了したかどうかを判断することなく、契約期間満了後の平成27年4月1日以降について、労働契約上の地位の確認及び賃金の支払を認容した部分は認められない。その理由は、次のとおりである。
最後に締結した労働契約は平成26年4月1日から平成27年3月31日までを契約期間としていて、第1審が終結する時点で契約期間が満了していたことは明らかであるから、第1審は従業員の請求内容を判断する際に、この事実を汲み取る必要があった。
そして、第2審は、契約期間の満了によって労働契約が終了したという会社の主張は、時機に後れたものとして却下して、これに対する判断をすることなく、従業員の請求を認容した。
第1審が汲み取るべきであった事実については、第2審で時機に後れたものとすることはできない。また、会社の主張が時機に後れたからといって、汲み取るべきであった事実を汲み取らないで、従業員の請求内容を判断することはできない。
ところが、第2審は最後に締結した労働契約の契約期間が満了した事実を汲み取らないで、契約期間の満了によって労働契約が終了したかどうかを判断しないまま、労働契約上の地位の確認及び賃金の支払を認めた。
第2審の判断には抜け落ちている部分があるので、破棄せざるを得ない。従業員が契約期間の満了後も労働契約は継続していると主張していたことを踏まえて、労働契約が終了したかどうか更に審理を尽くすため、原審に差し戻す。
朝日建物管理事件 解説
有期労働契約を締結していた従業員が、契約期間の途中で会社に解雇されて、解雇の無効を訴えた裁判例です。解雇の無効を主張する裁判はよくありますが、最高裁判所まで持ち込まれるケースは少ないです。この裁判では、特殊な経緯がありました。
第1審は、契約期間の途中の解雇は無効と判断して、従業員の主張を認めました。
そして、会社は、仮に契約期間の途中の解雇は無効としても、契約期間の満了によって雇止めが成立していると主張して控訴したのですが、第2審は、時機に後れた主張として、雇止めの効果は検討しないまま、第1審と同様に解雇は無効と判断しました。
時機に後れた主張については、民事訴訟法(第157条)によって、次のように規定されています。
「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」
訴訟が遅延して長期化を招く恐れがあることから、当事者に対して、訴訟の進行状況に応じて適切な時期に主張することを義務付けていて、後から新しい主張をしても裁判所は却下できることになっています。
この裁判例では、第1審が進んでいる最中に、最後に締結した有期労働契約の期間が満了したのですが、会社は契約期間の途中の解雇が有効であると主張しただけで、契約期間満了による雇止めを主張しませんでした。
最高裁判所は、契約期間満了による雇止めについては、本来は第1審が汲み取るべき事実であったから、会社の主張は時機に後れたものとは言えないと判断しました。そして、雇止めが有効か無効か改めて審理をする必要があると判断して、高等裁判所に差し戻しました。
会社にとってこのような親切な判断が下されないことも十分に考えられますので、会社が有期労働契約の契約期間の途中で解雇をして、その効力を争う場合は、会社は契約期間満了による雇止めの主張も並行して行うべきです。
その前に、横領などの悪質な違反行為がない限り、契約期間の途中で解雇をするべきではありません。解雇が無効と判断される可能性がある場合は、雇止めの方が有効と認められやすいので、契約期間が満了するまで待つことも大事です。
有期労働契約の場合は、契約期間の途中で解雇をしても、無期労働契約の場合と比べて、有効と認められにくいです。
有期労働契約の場合は、契約期間は労使間で合意している事項ですので、会社は契約期間が満了するまで雇用を保障していると考えることができます。労働契約法(第17条)では、「やむを得ない事由」がなければ解雇をしても認められないことが規定されています。
一方、無期労働契約の場合は、会社が無期限に雇用を保障するものではありません。仮に、保障するとしても、有期労働契約の場合と比べると緩やかな保障になります。労働契約法(第16条)では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は解雇をしても認められないことが規定されています。
「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合」より、「やむを得ない事由」の方が限定されていることが分かります。
また、従業員が雇用の継続(有期労働契約の更新)を希望している場合に、契約期間の満了によって会社が雇止めをするときは、無期労働契約の場合の解雇と比べると、有効と認められやすいです。ただし、従業員に更新を期待させないように注意をする必要があります。
【有効と認められやすい】=契約期間満了による雇止め<無期労働契約の解雇<有期労働契約の契約期間中の解雇=【有効と認められにくい】

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。