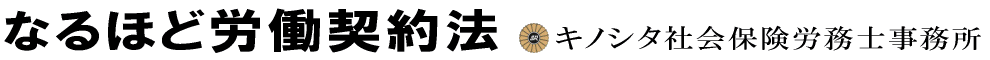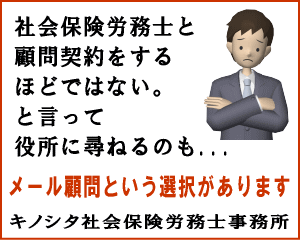進学ゼミナール予備校事件
進学ゼミナール予備校事件 事件の経緯
大学受験予備校の非常勤講師として、期間を定めて採用されました。その後、雇用契約を2回更新して勤務していたのですが、大学受験予備校は3回目の更新を拒否して、契約期間の満了を理由にして、講師を雇止めしました。
これに対して講師が、雇止めは無効であると主張して、雇用関係が存続することの確認を求めて、大学受験予備校を提訴しました。
進学ゼミナール予備校事件 判決の概要
雇用契約は契約期間の満了によって終了したとする原審の判断は、正当として是認することができる。
大阪高裁(原審)
臨時工(臨時従業員)の契約期間の満了による雇止めの効力を判断する際は、東芝柳町工場事件のとおり、
- 臨時工が従事する仕事の種類や内容
- 勤務の形態
- 雇用契約の期間に関する会社の説明
- 雇用契約を更新(締結)する際の形式的な手続の有無
- 雇用契約を更新した回数
- 同様の地位の他の従業員の継続雇用の有無
等を考慮して、期間の定めのある雇用契約が期間の定めのない雇用契約と実質的に同じ状態と認められる場合、又は、それほどの事情はないとしても、従業員が契約期間の満了後に雇用の継続を期待することに合理性があると認められる場合は、解雇に関する法理を類推適用するべきである。
この臨時工(臨時従業員)に関する法理は、原則として、予備校の非常勤講師として勤務する者と締結した雇用契約にも当てはまる。そこで、この視点に立って判断を進める。
講師の主張に沿う事実として、以下の事項が認められる。
- 雇用契約の期間については、契約時に予備校から講師に対して具体的な説明をしておらず、明確に定めた契約書も作成していない。ただし、基本的な授業は2学期が終わる12月で終了するという説明はしていた。また、1月・2月の直前講習や夏季・冬季の特別講習についても、その都度、契約書を作成しないで、口頭で約束していた。
- 講師と予備校の雇用契約は、4月から12月までの基本的な雇用期間で見ると、2回更新をして、予備校から雇止めされるまで2年8ヶ月非常勤講師として勤務していた。
- 講師は授業に熱心で、副教材を作成するなど、授業以外にもその準備のためにかなりの時間を費やしていた。
- 予備校は、講師から労働条件の改善を要求されるまでの間は、講師の勤務態度に満足していて、予備校から専任講師として勤務してはどうかと申し入れたことがあった。
これらの事実によって、本件の雇用契約が期間の定めのない雇用契約と実質的に同じ状態とは認められないとしても、少なくとも、雇用契約は継続されると講師が期待することに合理性があると推認できる。
しかし、本件の雇用契約について、この推認を妨げる以下の事情が認められる。
- 講師の勤務形態はいわゆる非常勤で、一定時間の授業を週一定のコマ数(5~7コマ)担当するもので、必ずしも毎日出勤するものではない。出勤する日も拘束されるのは、原則として授業時間だけで、その準備をする時間や程度、内容は個々の講師に委ねられていた。
- 講師は、専任講師にならないかという予備校からの申し入れを断っていた。
- 小規模の予備校の性格上、年度によって生徒数が大きく変動し、生徒の希望が変わることから、年度ごとに各教科の授業の時間数が変動した。そのため、必要な講師の数も必然的に変動せざるを得ない状況であった。
- 予備校の講師は大学院に通学したり、他の塾や予備校で勤務したりして、掛け持ちで勤務する者が多かった。そのため、各教科の時間割は、個々の講師の都合を聴いて調整した上で決定していた。
- 予備校の講師は長期間雇用されている者より、1年から3年程度で退職する者の方が多く、再雇用が当然といった状態ではなかった。1年目から2年目に年度が代わる際に契約が更新されない場合が多く、3年目以降も本人が希望すれば更新される場合が多かったが、確実ではなかった。
- 予備校の教育は、本来の教育というより大学に合格するための準備という性格が強く、大学や高等学校と比べると、企業としての要素が大きい。また、京都市は大手や中小規模の予備校が乱立してしのぎを削る状況であった。
このような事情は、大学受験のための小規模の予備校という業態の性格から、構造的・必然的に導き出されるもので、こうした観点から見ると、講師の勤務は、その勤務形態から製造業における臨時工の勤務と同一視することはできない。
講師の勤務は、長期間勤務することを期待して行われる私立大学等の常勤講師より継続性や拘束性が弱く、私立大学等の非常勤講師に近いと考えられる。また、講師の勤務の拘束性を考えた場合、大学受験予備校という業態を考慮するべきで、その点から見ても、講師の勤務は臨時工のそれには当てはまらない。
以上により、本件の雇用契約が継続すると講師が期待することに合理性があると認めることはできない。
進学ゼミナール予備校事件 解説
大学受験予備校と講師の間で、期間を定めた雇用契約を2回更新して、大学受験予備校が3回目の更新を拒否、雇止めをしてトラブルになったケースです。
期間を定めて雇用した場合の雇止めについては、東芝柳町工場事件によって、期間の定めのない雇用契約と実質的に同じような場合、又は、従業員が雇用の継続を期待することに合理性が認められる場合は、解雇に関する法理を適用することが示されています。
その場合は、正当な解雇理由があるかどうかを判断するのですが、会社が雇止めを想定していたときは、正当な解雇理由がないケースが一般的です。そうなると、解雇(雇止め)は無効になって、会社はそれまでの賃金を全額支払った上で、従業員は職場に復帰することになります。
なお、期間の定めのない雇用契約と実質的に同じと言えるかどうか、従業員が雇用の継続を期待することに合理性があるかどうかを判断するために、次のような事項を総合的に考慮することになっています。
- 臨時工が従事する仕事の種類や内容
- 勤務の形態
- 雇用契約の期間に関する会社の説明
- 雇用契約を更新(締結)する際の形式的な手続の有無
- 雇用契約を更新した回数
- 同様の地位の他の従業員の継続雇用の有無
これらの事項について、総合的に考慮してどちらか決まるのですが、通常は裁判例のように両方(会社にとって有利・不利)に分かれますので、判断の予測は難しいです。
また、労働契約法(第19条)によって、従業員が更新を希望して、次のいずれかに該当する場合は、前回と同一の労働条件で労働契約を更新することが示されています。この裁判になった事件は、労働契約法が施行された2008年より前のものですが、考え方は同じです。
- 有期労働契約の更新を繰り返して、期間の定めのない労働契約と同視できると認められる場合
- 従業員が、有期労働契約が更新されると期待することに合理的な理由があると認められる場合
雇止めの典型的なトラブルは、この裁判例のように、従業員が「更新される」と思っていたのに更新されなかった場合です。従業員が雇用の継続を現に期待しているからトラブルになる訳で、そのように期待する合理的な理由が存在するケースが多いです。
したがって、会社が有期労働契約の更新を拒否、雇止めをしてトラブルになった場合は、会社の主張は認められにくいです。
しかし、この裁判では、小規模の大学受験予備校という業態が大きく影響して、年度ごとに状況が変わること、長期間雇用されている者が少なかったこと、非常勤で毎日出勤していなかったこと等から、雇用契約の更新を期待することに合理性はないと判断しました。
有期労働契約の更新を繰り返していた場合に、このような雇止めに関するトラブルを防止するためには、最後の雇用契約を締結するときに、雇用契約書に「更新しません」と明示する方法が効果的です。口頭でも説明をしていれば、従業員が次回の更新を期待することはないでしょう。
このような明示をしていなければ、従業員は「前回と同様に更新される」と期待するのは当然です。更新を期待しないで諦めてもらうために、会社として何の手段も講じないまま、先送りして、いきなり雇止めをするとトラブルになりやすいです。
最後の雇用契約を締結する際に、従業員から会社に対して不信感を持たれる恐れがありますが、雇止めに関するトラブルが生じた場合のリスクと比較すればベターな方法と思います。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。