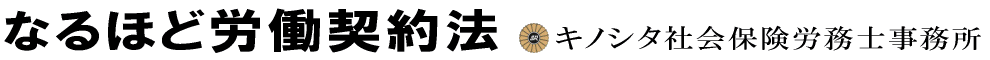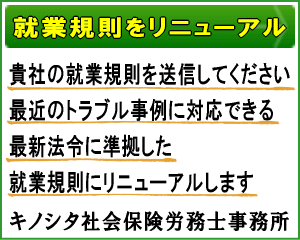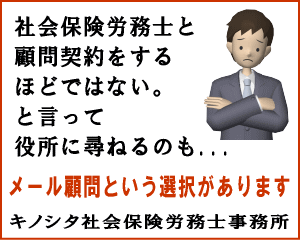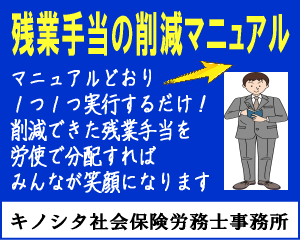ナショナル・ウエストミンスター銀行事件(整理解雇)
ナショナル・ウエストミンスター銀行事件 事件の経緯
外資系の銀行が、特定の業務部門を廃止することを決定しました。
その業務を担当していた従業員の賃金水準を維持したまま、他に配置転換できるポジションがなかったため、銀行は特別に退職金を上乗せして退職勧奨をしたのですが、従業員は拒否しました。
その後、銀行は関連会社に転籍することを提案したのですが、従業員はこれも拒否しました。
最終的に銀行は、退職勧奨をした際に提示した金額を上回る退職金を振り込んで、従業員の再就職先が見付かるまで、人材紹介会社の斡旋サービスを受けるための費用を支払うことを約束して、従業員を解雇しました。
これに対して従業員が、銀行が行った解雇は解雇権の濫用により無効であると主張して、労働契約上の地位の確認と賃金の支払を求めて、銀行を提訴しました。
ナショナル・ウエストミンスター銀行事件 判決の概要
余剰人員を削減するために解雇される従業員にとっては、再就職できるまで生活の維持に重大な支障が生じ、再就職にも相当の困難が伴うことが明らかである。
余剰人員を他の部署で活用することが経営上合理的と考えられる場合は、雇用を維持するべきである。
余剰人員を他の部署で活用することが不可能で、解雇することに合理的な理由があったとしても、その従業員の当面の生活の維持や再就職の便宜を図るために相応の配慮を行うと共に、従業員から納得を得るために解雇せざるを得なくなった事情を説明したり、誠意をもって対応することが求められる。
このような観点から、本件解雇が解雇権の濫用に当たるかどうか検討する。
なお、従業員は、本件解雇が解雇権の濫用に当たるかどうかは、いわゆる整理解雇の4要件を満たしているかどうかを検討して判断するべきと主張する。しかし、整理解雇の4要件は、解雇権の濫用に当たるかどうかを判断する際の考慮要素を類型化したものであって、全ての要件を満たさなければならないものではなく、解雇権濫用の判断は、本来、事案ごとの個別具体的な事情を総合的に考慮して行うものである。
銀行としては、従前の賃金水準を維持したまま他のポジションに配置転換できなかったのであるから、雇用を継続することは不可能であった。したがって、従業員を解雇したことについては、合理的な理由があったと認められる。
銀行は、年収650万円で関連会社に転籍するよう従業員に提案したが、当時、このポジションには年収450万円で契約社員が就いていて、退職の予定がなかったにもかかわらず、この契約社員を解雇してまで提案したものである。従業員に提示した年収650万円という金額は、市場価格としては最高額で、更に銀行は、賃金減少分の補助として、退職後1年間は200万円を加算して支給すると提案していた。
また、銀行は労働組合と従業員の処遇について、3ヶ月に渡って7回の団体交渉を行い、解雇せざるを得ない事情について繰り返し説明していた。
このような経緯から、銀行は誠意をもって対応していたと言える。
本件解雇には合理的な理由があり、銀行は、従業員の当面の生活の維持や再就職の便宜を図るために相応の配慮を行い、かつ、解雇せざるを得ない理由について従業員に繰り返し説明したり、誠意をもって対応していたこと、その他の事情を総合的に考慮すると、解雇権の濫用は認められない。
ナショナル・ウエストミンスター銀行事件 解説
銀行が整理解雇をしてその正当性が争われたのですが、この裁判では、整理解雇の4要件を否定して、4つの要素を総合的に考慮して判断することが示されました。
4つの要素のいずれかを満たさなくても、整理解雇を有効とする余地があることから、4要件の枠組みと比較すると、解雇の条件が緩和されたと言えます。
整理解雇については、法律で定められている内容ではありませんので、裁判所は、その時々の時代を反映して柔軟に判断していることが窺えます。
なお、整理解雇の4要件を採用した東洋酸素事件は昭和54年(1979年)、このナショナル・ウエストミンスター銀行事件は平成12年(2000年)の裁判です。
当事者としては予見が難しくなりますが、4要件としても4要素としても、どちらであっても4つの観点から、会社としてできることがないか仔細に検討することが欠かせません。
この裁判では、会社が相応の配慮をしていたり、整理解雇について繰り返し説明や協議を行ったりしていたことを評価して、整理解雇は有効と判断しました。
中小零細企業では、金銭的な面で大きな補助をすることは困難ですが、粘り強く説明や協議をすることは可能です。解雇は従業員にとって一大事です。会社としては拙速にならないように、できることがないか慎重に検討して対応するべきです。
なお、労働契約法の研究会では、整理解雇の4要件や4要素にこだわらない裁判も見られることから、労働契約法に取り入れることは見送られました。
【関連する裁判例】