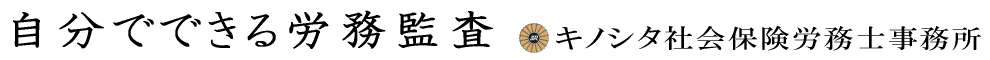労働基準法に違反する罰金制度
労働基準法に違反する罰金制度
- 遅刻、欠勤、目標の未達、喫煙、物品の損壊、仕事上のミス等に対して、罰金制度を設けていませんか?
- 実際の損害額に関係なく、予め一定の額を定めて罰金を科すことは、労働基準法に違反します。
【解説】
次のような罰金制度を設けている会社があります。
- 遅刻をしたときは、○円の罰金
- 欠勤をしたときは、○円の罰金
- 販売目標やノルマを達成できなかったときは、○円の罰金
- 指定場所・指定時間以外で喫煙をしたときは、○円の罰金
- 物品を壊したときは、○円の罰金
- 不良品を出したときは、○円の罰金
よくありそうな話ですが、原則的には、労働基準法に違反する行為です。労働基準法(第16条)によって、次のように規定されています。
「賠償予定の禁止」と呼ばれる規定で、2つの内容が定められています。
労働契約の不履行について違約金を定めることが禁止されています。労働契約の不履行とは、約束に違反した場合のことを言います。具体的には、労働時間、労働日、販売目標やノルマの達成、喫煙のルール等が労働契約(約束)に当たります。
遅刻や欠勤は、予め定めていた労働時間や労働日の約束(労働契約)に違反する行為です。そのような約束に違反したときに、従業員に「違約金=罰金」を支払わせる行為は、労働基準法違反に該当します。
損害賠償額を予定する契約をすることも禁止されています。従業員の故意や重大な過失(不注意)によって、物品を壊したり、不良品を出したりして、会社に損害が生じたときは、原則として、会社は従業員に損害賠償を請求することができます。
損害賠償“額”を予定していることが重要で、実際の損害額に関係なく、「1,000円を支払え」というように予め一定の額を設定する契約(約束)は、労働基準法違反になります。
最初に列挙したような罰金制度は全て、基本的には、この規定に違反しています。もし、従業員が労働基準監督署に駆け込むと、労働基準法違反として、会社は是正勧告を受けることになります。
しかし、罰金制度ではなく、制裁処分(懲戒処分)として行う減給は、労働基準法によって認められています。労働基準法(第91条)によって、次のように規定されています。
減給の額が1回の違反行為につき平均賃金の1日分の半額以内であれば、減給処分を行えます。また、違反行為が複数回あったときは、減給の総額を1ヶ月の賃金総額の10分の1以内にする必要があります。
例えば、平均賃金が1日1万円の従業員については、1回の違反行為につき5千円以内であれば減給をしても、労働基準法上は問題ありません。ただし、会社が減給処分をするときは、いくつか注意点があります。
- 就業規則に、制裁処分(懲戒処分)の種類・程度、及びその事由(違反行為)を規定すること
- 懲戒事由(違反行為)の内容と制裁処分(懲戒処分)の程度が釣り合っていること
懲戒処分をするときは、その根拠として就業規則で定める必要があります。また、労働契約法(第15条)によって、一般常識で考えて、違反行為に対して厳し過ぎる懲戒処分は無効になります。
例えば、10分の遅刻をしたときに、平均賃金が1万円の従業員について5千円を減給することは、一般常識で考えると厳し過ぎると思います。従業員が遅刻をしたときは、口頭で注意や指導をして、それでも遅刻を繰り返したときは、最初の懲戒処分は始末書を提出させる譴責(戒告)処分が妥当です。その都度、適切な対応を検討する必要があります。
ところで、皆勤手当を支給して、遅刻や欠勤をしたときに、皆勤手当を減額している会社があります。これは罰金制度ではなく、不支給が基本で、無遅刻・無欠勤だった場合の報奨金として、皆勤手当を支給していると考えられますので、違法にはなりません。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。