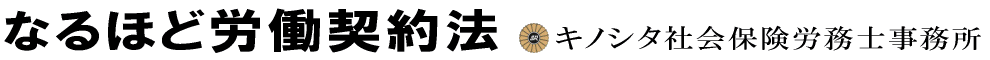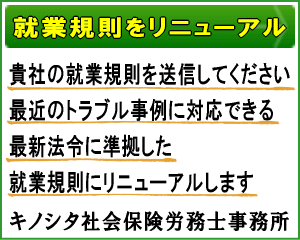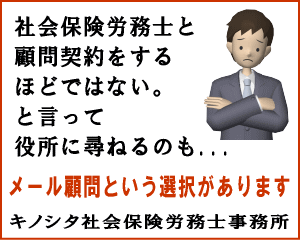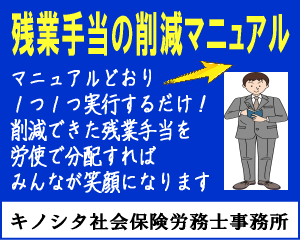メトロコマース事件
メトロコマース事件 事件の経緯
東京メトロの駅構内で売店事業を行う会社には、正社員、契約社員B、契約社員Aという名称の雇用形態の区分が設けられていました。
正社員は無期労働契約で、定年は65歳と定められていました。正社員は、本社の経営管理部、総務部、リテール事業本部、ステーション事業本部の各部署や各事業所に配置され、配置転換、職種転換、関連会社への出向を命じられることがあり、正当な理由がない限り、拒否できませんでした。
また、退職金規程により、正社員には、退職金として本給に勤続年数に応じた支給月数を乗じた金額を支給することが定められていました。
契約社員Bは有期労働契約で、原則として契約は更新され、定年は65歳と定められていました。契約社員Bの業務は、売店での販売とそれに付随する業務で、勤務する売店の変更を命じられることはありましたが、業務内容に変更はなく、配置転換や出向を命じられることはありませんでした。契約社員Bには、退職金は支給されませんでした。
契約社員Aは、契約社員Bのキャリアアップの雇用形態として位置付けられ、同様に有期労働契約で、原則として契約は更新され、定年は65歳と定められていました。契約社員Aにも退職金は支給されませんでしたが、後に、契約社員Aは職種限定社員に名称が改められ、無期労働契約に変更されて退職金が支給されることになりました。
正社員、契約社員B、契約社員Aが売店で販売業務等を行っていましたが、それぞれの業務内容は同じでした。
ただし、正社員は、売店で欠勤した者に代わって代務業務を行ったり、複数の売店を統括して、売上げ向上の指導・改善、事故対応のサポート、トラブル処理等のエリアマネージャーの業務に従事することもありました。契約社員Aも代務業務を行っていましたが、契約社員Bは代務業務を行うことはなく、エリアマネージャーの業務に従事することもありませんでした。
会社には、契約社員Bから契約社員A、契約社員Aから正社員への登用制度が設けられていて、原則として勤続1年以上の希望者全員に受験が認められていました。
そして、契約社員Bとして採用された者が、約10年間、有期労働契約の更新を繰り返して、65歳で定年退職しました。退職金が支給されないことは労働契約法の第20条に違反すると主張して、退職金の支払いを求めて、会社を提訴しました。
メトロコマース事件 判決の概要
労働契約法第20条は、有期労働契約の従業員と無期労働契約の従業員の労働条件が相違する場合に、不合理な相違を禁止した規定である。労働条件の相違が退職金である場合は、その会社における退職金の性質や支給する目的を踏まえて、同条所定の諸事情を考慮した上で、不合理であるか否かを判断することになる。
退職金が支給される正社員は、本社の各部署や各事業所に配置され、配置転換等を命じられることがあった。また、退職金は、本給に勤続年数に応じた支給月数を乗じた額となっていて、本給は、年齢によって定められる部分と職務遂行能力に応じて定められる職能給の部分があった。
退職金の支給要件や支給内容等に照らすと、退職金には職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた賃金の後払いや継続的な勤務に対する功労報償等の複合的な性質があり、会社は正社員として職務を遂行し得る人材の確保や定着を図ることを目的として、様々な部署で継続的に就労することを期待する正社員に対して退職金を支給していたと認められる。
そして、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容(業務の内容及び責任の程度)を比較すると、共通する部分が多いけれども、次のように一定の相違があった。
- 正社員は、代務業務を行っていた
- 正社員は、エリアマネージャーの業務に従事することがあった
- 契約社員Bは、売店業務にだけ従事していた
また、正社員は、配置転換を命じられる可能性があり、正当な理由がない限り、拒否できなかったのに対して、契約社員Bは、勤務する売店の変更を命じられることはあっても、業務内容に変更はなかった。両者の変更の範囲についても、一定の相違があった。
更に、会社は、契約社員A及び正社員への登用制度を設けて、相当数の者を登用していた。これについては、労働契約法第20条の「その他の事情」として考慮するのが相当である。
退職金の複合的な性質や支給する目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すると、契約社員Bの有期労働契約は原則として更新され、定年が65歳と定められる等、短期雇用を前提としていないこと、約10年勤続していたこと、を汲み取っても、両者に退職金の支給の有無という労働条件の相違があることは、不合理とは言えない。
以上により、売店業務に従事する正社員に退職金を支給する一方で、契約社員Bに退職金を支給しないという労働条件の相違は、労働契約法第20条の不合理に当たらない。
メトロコマース事件 解説
同一労働同一賃金に関する最高裁判決で、退職金が争点になったケースです。
一般的に、退職金には賃金の後払い、功労報償等の性質があり、人材の確保や定着を図ることを目的として支給するものと考えられています。したがって、長期雇用を前提とする無期雇用の正社員に退職金を支給し、短期雇用を前提とする有期雇用の契約社員やパートタイマー等に退職金を支給しないという制度には合理性があります。
ところが、この会社では、同じ売店業務に従事する正社員と契約社員がいて、契約社員は有期雇用だったのですが、約10年間も勤続する者がいたりして、長期雇用が前提になっていました。高裁では、退職金の内、長年の勤務に対する功労報償に当たる部分も支払わないのは不合理であると判断して、正社員の支給基準で計算した額の4分の1を支払うよう命じました。
一方、最高裁は、退職金には複合的な性質があり、正社員として職務を遂行し得る人材の確保や定着を図ることを目的として支給していることを認めました。これを踏まえて、次の事情を考慮した上で、契約社員には退職金を支払わなくても良いと判断しました。
- 正社員は、エリアマネージャーの業務に従事することがあった
- 正社員は、配置転換等を命じられる可能性があった
- 正社員への登用制度が設けられていた
高裁とは違い、功労報償に当たる部分を切り離して計算するような方法は採用しませんでした。
この会社における判断ですので、他社では違う結論になる可能性がありますが、“正社員として”職務を遂行し得る人材の確保や定着を図ることを目的として支給する「退職金」と「賞与」(大阪医科大学事件)については、会社の裁量が認められやすい傾向が示されたと思います。更に、これらの裁判では、正社員への登用制度があったこともポイントになったと考えられます。
また、通常、退職金制度を運用するためには、長期間にわたって原資を積み立てる必要がありますので、退職金制度の内容については、会社の裁量が尊重されるべきと考えられています。この点も考慮して慎重な判断になったのかもしれません。
【関連する裁判例】