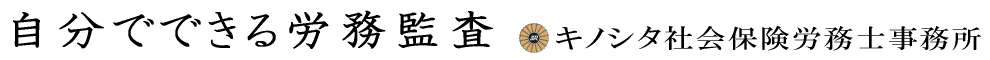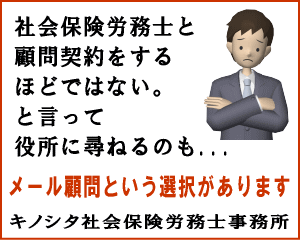フレックスタイム制の割増賃金の計算方法
フレックスタイム制の割増賃金の計算方法
- フレックスタイム制を採用している場合、割増賃金(時間外勤務手当)の計算方法は適正ですか?
- 原則として、1日8時間又は1週40時間を超えた労働時間が割増賃金の対象となりますが、フレックスタイム制を採用している場合は、計算方法が特殊です。
【解説】
労働基準法(第37条)によって、法定労働時間を超えた時間(時間外労働の時間)に対して、割増賃金を支払うことが義務付けられています。原則的には、1日8時間又は1週40時間を超えて労働した時間が、割増賃金の対象となります。
しかし、フレックスタイム制を採用している場合は、清算期間を平均して1週40時間以内であれば、8時間を超える日又は40時間を超える週があったとしても、時間外労働にはなりません。
フレックスタイム制とは、出退勤の時刻を従業員の決定に委ねる制度ですので、割増賃金の計算方法が特殊です。
割増賃金の支給基準となる法定労働時間は、清算期間の暦日数に応じて、次のようになります。「40時間/7日×暦日数」で計算した時間で、これを超えた労働時間が時間外労働の時間として、割増賃金の支給対象になります。
| 清算期間の暦日数 | 法定労働時間 |
|---|---|
| 31日 | 177.1時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 28日 | 160.0時間 |
清算期間の所定労働時間は、この範囲内で設定する必要があります。例えば、清算期間の暦日数が31日の月において、1日の所定労働時間が7.5時間、所定労働日数が23日とすると、その月の所定労働時間は172.5時間になります。
労働基準法上は、法定労働時間の177.1時間を超えた時間に対して、割増賃金(125%の時間外勤務手当)を支払うことが義務付けられています。
「177.1時間-172.5時間」の4.6時間分(法定労働時間内で所定労働時間を超えた時間)については、就業規則や雇用契約書の内容によります。
例えば、就業規則や雇用契約書で「所定労働時間を超えた時間に対して、125%の時間外勤務手当を支払う」と記載している場合は、そのように支払います。
一方、「法定労働時間を超えた時間に対して、125%の時間外勤務手当を支払う」「所定労働時間を超えた時間に対して、100%の時間外勤務手当を支払う」と記載している場合は、4.6時間分については、通常の100%の賃金を支払うことになります。
また、フレックスタイム制を導入している場合であっても、深夜の時間帯(22時から翌日5時まで)の労働時間に対して、25%の深夜勤務手当を支払う義務があります。
更に、法定休日労働をしたときは、135%の休日勤務手当を支払う義務があります。この法定休日労働の時間については、時間外労働の時間を計算するときは除外します。除外しないと、時間外勤務手当と重複して支払うことになります。
以上のとおり、フレックスタイム制を採用している場合であっても、1ヶ月の実働時間の合計を把握するだけでは不十分ですので、各日ごとの実働時間を適正に把握しないといけません。
また、年次有給休暇を取得した場合は、取得日数分の所定労働時間を1ヶ月の実働時間に加算します。それによって法定労働時間を超えたときは、割増賃金(125%の時間外勤務手当)を支払う必要があります。
完全週休二日制の場合
暦日が31日の月は177.1時間が法定労働時間になりますが、完全週休二日制の会社に限って、例外的な取扱いが認められています。
例えば、土曜日と日曜日が休日の完全週休二日制、1日の所定労働時間が8時間、賃金計算締切日が毎月末日の会社で、7月1日が月曜日だったとします。
この場合、7月の所定労働日数は23日ですので、1ヶ月の所定労働時間は184時間(23日×8時間)になります。
177.1時間の法定労働時間を超えますが、完全週休二日制ですので、各週の所定労働時間は40時間です。これまでは一切残業をしなかったとしても、177.1時間を超えた時間に対して、割増賃金の支払いが義務付けられていました。
曜日の巡りによって想定外の時間外労働が発生していましたが、労働基準法が改正されて、労使協定で「清算期間の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることを定めた場合は、そのように処理できるようになりました。
上の例で言うと、「23日×8時間=184時間」が労働時間の限度になりますので、このとおりの勤務で残業をしなければ、時間外労働の時間(割増賃金の支払い義務)は発生しません。
同様に、7月1日が土曜日だったとすると、「21日×8時間=168時間」が労働時間の限度になります。これを超えた時間が時間外労働の時間として、割増賃金の支払い義務が生じます。
1年間の合計時間で比較すると、労使協定で定めた場合、通常の方法で計算した場合は同じになります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。
もっと詳しく
- 労働基準法 第32条の3<フレックスタイム制>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第32条の3第3項<完全週休二日制のフレックスタイム制>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第37条<残業手当>【なるほど労働基準法】
- フレックスタイム制【労務管理の知恵袋】
- 割増賃金の計算方法【労務管理の知恵袋】
- 他のページも見てみる【自分でできる労務監査】
- 割増賃金の基礎となる賃金は、正しく計算していますか?
- 時間外労働等をしたときは、正しい割増率で割増賃金を支払っていますか?
- 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入して、割増賃金の計算方法は適正ですか?
- 1年単位の変形労働時間制を導入して、割増賃金の計算方法は適正ですか?
- フレックスタイム制を導入している場合、割増賃金の計算方法は適正ですか?
- 時間給に換算する際に、1ヶ月平均所定労働時間数は何時間で計算していますか?
- 30分未満の残業時間を切り捨てて計算していませんか?
- 振替休日や代休を与えた場合の賃金の計算方法は適正ですか?
- 1ヶ月60時間を超える時間外労働に対して、150%の割増賃金を支払っていますか?