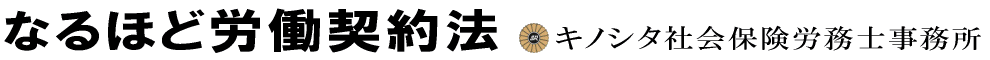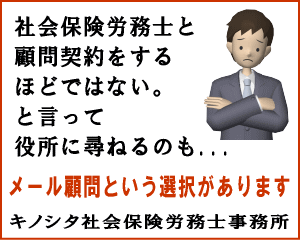崇徳学園事件
崇徳学園事件 事件の経緯
学校法人で事務局次長として勤務していた者について、次のような事実がありました。
- 台風災害の復旧工事に関して、事務組織規程、決済規程、経理規程等に違反して、適切な事務処理、会計処理をしないで、工事の請負業者に工事代金の不当な水増し請求をさせて、学校法人に損害を与えた。
- リース契約に関して、必要がないにもかかわらず、クレジット会社との間に別の会社を置き、虚偽のリース契約をして、学校法人に損害を与えた。
- 職務専念義務に違反するなど勤務態度が劣悪で、学校法人の職員としての適格性を欠く行為が多々あった。
これらの行為を理由として、学校法人は就業規則に基づいて、事務局次長を懲戒免職(懲戒解雇)しました。
これに対して職員(事務局次長)が、懲戒免職(懲戒解雇)の無効を主張して、職員としての地位の確認と賃金の支払を求めて学校法人を提訴しました。
崇徳学園事件 判決の概要
台風被害に遭い、学校法人は保険会社から約3000万円の保険金を受け取ることになったが、職員は保険会社に対して、保険金を直接工事業者に振り込むよう指示をした。
職員はその処理について、正規の決裁手続をしないで、保険金を受領した事実及び復旧工事代金を支払った事実を会計帳簿に記載しなかった。
このような支払方法を主導し、実行したのは職員(事務局次長)で、理事長の意向に沿ったものであったとしても、正規の決裁手続(適正な会計処理)をしなかった責任は職員(事務局次長)にある。
職員は保険会社から学校法人に復旧工事代金を超える保険金を支払わせるよう画策して、保険会社から工事業者に保険金(復旧工事代金)を直接振り込ませることによって、保険会社から支払われた保険金と復旧工事代金の差額を工事業者に取得させた。
しかし、損害保険契約に基づいて支払われた保険金は、正当な金額であれば学校法人に帰属するものであるし、過大な部分があれば学校法人は差額を返還する義務がある。職員の行為によって、学校法人は損害を受けたと言える。
そして、職員の行為は、生徒の父母、学校関係者、監督行政庁、更には社会一般から、学校法人が不正行為をしているという疑惑を招くものであって、著しく不相当な行為である。
その結果、学校法人の関係者から、復旧工事に関連する保険金の支払について、職員が不正行為をしたのではないかと指摘があった。
県知事は学校法人に対して、台風被害に対する保険金の収入及び復旧工事代金の支払を学校会計に計上していないことが法令及び寄附行為に違反すると指摘した上で、改善実施計画を作成して提出するよう求めて、学校法人に対する補助金の交付を保留した。
学校法人が著しく不相当な行為をしたと社会一般から非難され、信用を失墜したことについて、職員(事務局次長)は責任を免れない。
事務局次長は、職員としては事務局の最高責任者であったにもかかわらず、会計処理上違法な行為を行い、学校法人の信用を失墜させ、学校法人に損害を与えた。その責任を軽視することはできない。
また、職員は、特定の業者に契約に基づかない利得を与えて、これと深い結び付きがあったと見られてもやむを得ない。
そうすると、学校法人が職員を懲戒免職したことは、客観的に見て合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる。学校法人が行った懲戒免職は、懲戒権を濫用したものではない。
崇徳学園事件 解説
職員が不正な会計処理をしたことにより、学校法人に損害を与えて、信用を失墜させたことを理由として、学校法人が行った懲戒免職(懲戒解雇)が有効か無効か争われた裁判です。
一審では有効、二審では無効と判断が異なっていました。そして、最高裁では、懲戒免職(懲戒解雇)は有効と判断しました。
懲戒免職(懲戒解雇)について争われた裁判例で、労働契約法上は、解雇と懲戒の2つの規定が設けられています。
労働契約法の第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。
客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当であると認められる場合は、解雇は有効と判断されます。
また、労働契約法の第15条では、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と規定されています。
こちらの懲戒については前半に文章が置かれていますが、解雇と同じ枠組みで、客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当であると認められる場合は、有効と判断されます。
判断基準が抽象的なため、当事者が有効か無効か予測することは困難です。
一審と二審で判断が異なっていたことからも分かるように、程度の問題であったり、どの点を重視するかによって結論が違ってきます。社内で似たようなケースがあったとしても、懲戒解雇は無効と判断される可能性は十分あります。
そして、会社の行った解雇が無効と判断されると、会社に籍を戻した上で、解雇した以降も通常の勤務をしていたものとみなして賃金の全額を支払わないといけません。
解雇の無効を訴えて裁判になると、無効か有効か、いずれかの判断しか行われません。「解雇は有効だけれども、会社は300万円を支払え」というような双方に妥協を求めるような判決が出ることはありません。
裁判になると、主張が認められれば良いのですが、従業員にとっても会社にとってもリスクが大きいです。解雇は慎重に、できれば解雇以外の方法(退職勧奨など)で対処するのが賢明です。
なお、この事件は、職員が横領したり、不正に利益を得たりしたケースではありませんでしたが、横領については、解雇は認められやすい傾向にあります。
【関連する裁判例】
- 日本食塩事件(ユニオン・ショップ協定)
- 高知放送事件
- あさひ保育園事件(整理解雇)
- 崇徳学園事件(損害の発生)
- 学校法人松蔭学園事件(適格性の欠如)
- 日本ユニカー事件(逮捕・拘留による長期欠勤)
- 西武バス事件(バスの遅延)
- 新宿郵便局事件(懲戒処分後の解雇)
- セガ・エンタープライゼス事件(能力不足)
- フォード自動車事件(中途採用部長の能力不足)

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。